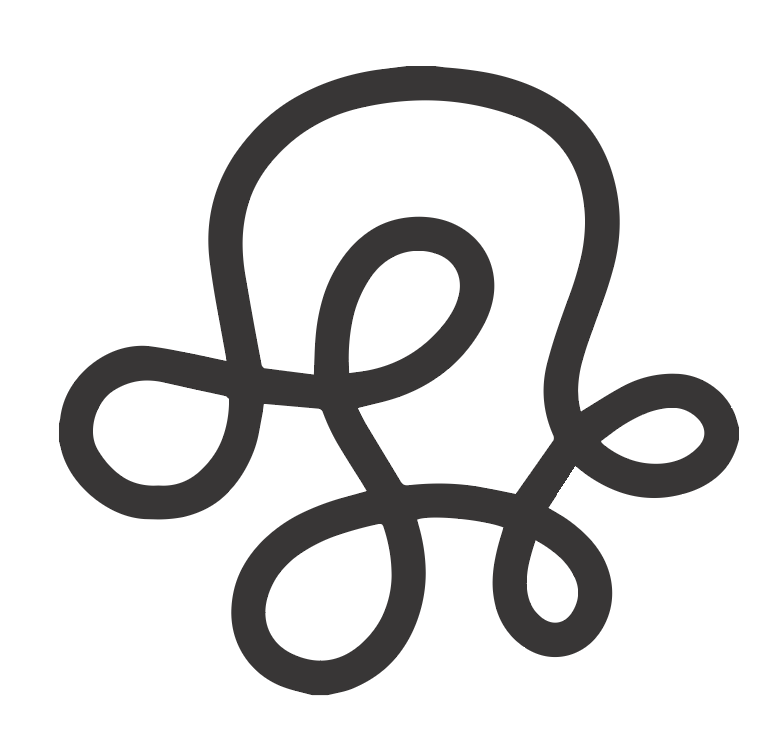苦味とは何か。警告のサインでもあり、癒しでもある存在【#006】
- 2025年8月16日
- 読了時間: 11分
更新日:2025年12月15日
危険を知らせるシグナル、苦味とは
___今回は苦味をテーマに伺います。
そもそも苦味とは一体何なのでしょうか?
味覚は大きく五つ ―甘味・塩味・酸味・旨味、そして苦味で構成されています。
甘味は糖=エネルギー源
塩味や旨味はミネラルやアミノ酸
といった 、生命活動の維持にポジティブに直結する味とも言えます。
しかし、苦味は少し毛色が違います。
エネルギーにもタンパク質にも直接つながらず、
むしろ 「これ、口に入れて大丈夫?」 と警告してくれる“危険信号”の役割を担っているんです。
___危険信号ですか。
例えば、毒キノコは苦いイメージがありますよね。
私たちの体は、苦味を感知すると「これは毒かもしれない」と判断し、
反射的に吐き出すようにできています。
特に幼い子どもの頃は何でも口に入れてしまいますが、「苦い」と感じた瞬間、それは食べ物ではなく、口に入れない方がいいというサインになります。
体内に取り込むべきではない可能性が高いため、反射的に吐き出すわけです。
誤飲を防ぐために、あえてペンのキャップなどに意図的に苦味成分を入れることがあります。
あれは赤ちゃんが飲み込まないように、吐き出させるためですね。

___「危険信号」としての役割は、人間以外の動物にも共通するのでしょうか?
はい。動物たちも、体に良くないものを間違って摂取しないように、この仕組みを持っています。
ただ、何が毒になるかは動物によって違います。
例えば、人間には無害でも、犬や猫にとっては有害な食べ物がありますから。
共通して言えるのは、人間もその他の動物も、苦味は「これは自分にとって安全か?」を判断するために極めて重要な情報なんです。
舌はほんのわずかな量でも苦味を感じ取れる
苦味の“感度”はトップクラス
味を感じる最小の量を「閾値(いきち)」と言います。
※閾値:人間がどのぐらいの量・強さだとその味を認識するかという値
食塩とか砂糖は、閾値は0.01ポイントぐらいなんですね。
それに対して苦味の閾値は他の味に比べて段違いに低い。例えば、キニーネという苦味成分は、0.00008ポイント。
砂糖の甘さに比べて約1250倍も少ない量で感知できます。
※キニーネ:苦味成分の一種。ジントニックのトニックウォーターなどにも含まれる
受容体の数が示す、苦味への本能的な警戒
___甘味や塩味と比較して、苦味は少量で感知できる。
これは危険信号としての苦味を敏感に察知するため体の構造なのですね。
そうなんです。
私たちの口の中には「味蕾(みらい)」と呼ばれる器官があって、そこで食べ物の味を感じ取っています。
味蕾の中には「味細胞」という細胞があって、そこには味をキャッチするための“センサー”のようなもの――「味覚受容体」というたんぱく質があるんです。
食べ物に含まれる甘味成分やうま味成分がこの受容体と反応することで、私たちは味を感じる仕組みになっています。
そして実はこの“センサー”、ただ味を感じるだけでなく、種類の多さからも人間の感覚の進化が見えてくるんです。
___センサーの数が五味それぞれに対して違うのですか?
たとえば、甘味を感じ取るセンサーは1〜3種類ほど。
それに対して、苦味を感知するセンサーはなんと26種類もあるんです。
26種類を組み合わせることで、人間は何百種類もの異なる苦味を識別できると考えられています。
センサーの種類の多さからも、いかに私たちが「苦味」に対して敏感に進化してきたかがわかりますよね。
___安全を守るために苦味を感じ取る必要があったのですね

「大人の味」の正体は、経験と快感のループ
___なぜ大人になると「苦味も美味しい」と感じるようになるのでしょうか?
子供と大人で、苦味に関する身体の変化が起きるのですか?
いえ、シンプルにいうと「慣れや経験」です。
苦味の受容体が増えるといったことではなく
子どもが大人になるにつれて、味の楽しみ方を学んでいくのです。
経験値の差によって摂取するものが変わり、それに伴って敏感に反応する香りや味も変わっていきます。
___慣れていく、というと具体的にはどういうプロセスなのでしょうか。
まず、子どもは大人が食べているものを見て、「あれは安全な食べ物だ」という情報を得ます。
「食べてもいいんだ」と試し、「苦いな」と思いながらもだんだん慣れて、その美味しさやバランスの良さに気づいていきます。
例えばピーマンも、最初はただ苦いから嫌だと。
しかし、大人が青椒肉絲を美味しそうに食べているのを見て、肉の旨味やタレの甘辛さとピーマンの苦味が合わさると美味しくなる、という経験をします。

子どもは安全かどうかの情報が少ないので、苦味の強いシグナルを単純に「不快」と判断します。
その中でも「どの食べ物なら苦くても大丈夫か」という情報や経験を、大人を見ながら少しずつ蓄積していきます。
最初は知識も経験もないため、苦いものは楽しいとは思えず本能的に吐き出すでしょう。
ここで重要なのは、周りの大人が「美味しいよ」と伝えてあげること。
大人が「苦いから嫌い」と言っていたら、子どもが挑戦する機会は永遠に失われてしまいますから。
___なるほど。
経験と、周りからの情報が組み合わさって、少しずつ「食べられる苦味」が増えていくわけですね。
そして、苦味を好んでいく変化の背景には「ストレス」があります。
ストレスは大人になるほど増えていくと言えるかもしれませんね。
人間はストレスを感じると、感覚全体が鈍くなる傾向があります。
例えば、暑さで味が分かりにくくなる、音がこもって不快に聞こえる、目がかすむといった経験はありませんか。極端な例は暗闇です。
何も見えず、聞こえず、状況を把握できないこと自体が、私たちに本能的な恐怖を感じさせます。それほど、感覚が遮断されることはストレスなのです。
___ストレスで感覚が鈍るからこそ、逆に強い刺激を求める、ということですか?
その通りです。
ストレスによって感覚が鈍り、
今度は感覚が鈍ること自体がさらなるストレスになるという、悪循環ですね。
人間はストレスと感覚の作用に敏感です。
そこで人間は、はっきりとした感覚を求めるようになります。苦味や酸味のようなシャープな刺激は、その鈍った感覚をリセットしてくれるんです。
酸味や苦味は少ない量でも強く感じられるため、そうした状況でも役立つわけです。

___疲れた時のコーヒー、仕事終わりに飲むビールの一口目、
人によって求める味はそれぞれですが、もしかしたら苦味に感覚のリセットを求めているのかもしれません。
その「ホッとした体験」が、「またあの感覚を味わいたい」という欲求に繋がります。この「体験→欲求→反復」というサイクルが、嗜好を育てる正体です。
嗜好性が育つにはそれなりに時間がかかる。
いきなり濃いホップのビールを飲んで美味しいと思うかは人による。
繰り返し飲んでビールが好きな人は、次にそれを飲んだら美味しいと思うかもしれません。
____嗜好は経験の積み重ねで時間をかけて出来上がるのですね。
大人になってストレスを感じる中で、刺激として苦味や酸味を取り入れると癒やされ、その経験が蓄積されます。
夏場の疲れた仕事の後にビールやレモンサワーを飲む、コンビニで必ずビールやレモンサワーを買って帰るといった行動は、すでに習慣化しています。
おいしいを超えて体の快楽になっていて、その情景を一度知るとまた欲しくなります。
繰り返すうちに習慣となり、苦味は単なる刺激から、複雑な喜びや癒しへと昇華されていく。

味わいの中心を担う「骨格」としての苦味
___ここで改めてお伺いします。
苦味は「美味しい」ものなのでしょうか、それとも「危険信号で美味しくない」のでしょうか?
二択で答えるのはなかなか難しいのですが、結論から言えば 「美味しい」 です。
もちろん、すべては バランス・個人の好み・その人が持つ味覚の歴史 によって変わってきます。
苦味は、甘味や塩味のようにエネルギー源やミネラルと結びつくわけではなく、
五味の中でもとても“嗜好性の高い味”だといえます。
しかも、非常に感知しやすい味覚なので、個人差が大きく、体調によっても感じ方が変わるんです。
“大人の味”と呼ばれる料理や飲み物が持つ 「複雑さ」 をつくり出しているのは、実はこのわずかな苦味。
ほんの少し加わるだけで、味に奥行きやキレを与えてくれる。とても興味深い味覚なんですよ。
そして、さきほどお話ししたように、そもそも苦味には「これは口にしても大丈夫?」と知らせてくれるセンサーのような役割があります。
苦味は“美味しさ”と“本能的な警戒”のはざまで、私たちの味覚を刺激し続けているんです。
では、「苦味」は料理や飲み物の中でどんな働きをしているのでしょうか?
今度は、“美味しさをつくる側”の視点で見てみましょう。
味わいと “バランス”
ここで味のバランスについて考えてみましょう。
例えば甘味と塩味 は “多過ぎると不快” につながります。
甘味が強すぎれば、子ども向けの飴のように単調で満足度ダウンの味に
塩味も一定ラインを超えると途端にしょっぱ過ぎとなる
適正バランスの量が分かりやすいのも、甘みや塩味ですね。
例えば日本人の定番・味噌汁や甲殻類スープは 塩分約0.8 % が “ちょうどいい” と言われます。
苦味がつくる奥行きと “骨格”
甘味・塩味・酸味だけでは、どうしても味が平板になりがち。
そこに ほんの少しの苦味 が加わると、複雑さやさっぱり感が生まれます。
苦味は、全体のバランスを整え、味に複雑さや奥行きを与える「骨格」のような役割を果たします。「味わいの中心は、苦味ではないか」とも考えられます。
実験例 甲殻類の味のバランスから知る苦味の重要性
ここで、
苦味の存在の大切さが分かる、ひとつの実験例をご紹介します。
日本の食品メーカーの方が研究したところ、カニやエビには「甘い」と言われる一方で、実はけっこう苦味成分が含まれていることが分かりました。
そして実験では加工品で“カニ味”を再現する際、カニの苦味成分を除いて残りの成分だけで味の合成を試みます。
カニやエビのおいしさを構成する成分は 8~9 種類ほど。
「そこから苦味を抜けばよりまろやかでおいしくなる」「もっと甘くておいしく感じるエビやカニ味になるだろう」と考えたのです。
____究極に甘みのある甲殻類の味ができそうです!
甘エビ以上に甘い、のような。
そう期待しますよね。
ところが苦味を抜いて作ってみると、カニの味やエビの味にもならなかったんです。
ぼやけた、締まりのない風味になってしまった。
このことは、苦味があるからこそ全体の味がまとまり、逆に甘味や旨味が引き立つという事実を端的に示しています。
普段意識しないほどのごく少量でも、苦味は人間に作用し、美味しさに直結しているわけです。
つまり苦味は、食べ物や料理の特徴をバランスよく整え、複雑さを与えているのかもしれません。
苦味は他の味覚たちをまとめ上げ、舞台全体に立体感を与える、いわば味の「骨格」なんです。

私たちと苦味の“これから”
___現代のわたしたちは苦味とどう付き合っていると感じますか?
間違いなく、以前よりずっと苦味を積極的に楽しんでいますね。
クラフトビール市場におけるIPA(インディア・ペールエール)の人気はその象徴です。
実際コンビニエンスストアにもIPA商品がこの10年で爆発的に増えています。
※IPA(インディア・ペールエール):ホップの香りと苦味がしっかり効いたビールのスタイル。クラフトビール人気の高まりとともに注目されている。
ジンブームも同様です。
ジントニックやジンソーダは甘味を抑えてドライ。苦味と甘味、さらに酸味もあって複雑な嗜好性の上に成り立っています。
これらはまさに、苦味の持つ複雑な魅力を楽しむ飲み物です。
ストレスの多い現代社会が、そうしたシャープな刺激を求めているのかもしれません。
また、苦味が味わいの中心になっているものを取る機会は確実に増えています。
日本の中にいても世界各国の料理を楽しめる環境が増えたことで、
人々がより複雑な味わいを求めるようになっていることも苦味がより注目される要因になっているかもしれません。

____確かに、複雑な味に出会いやすい環境になっているように思います。
健康志向やトレンドも後押ししています。
カカオ含有量の高いビターチョコレートが定番化したのも良い例です。
甘さを抑えながらも、カカオの持つ豊かな香りと苦味が満足感を与えてくれる。
心を癒してくれる存在として、苦味は現代人の良きパートナーになっていると言えるかもしれませんね。
編集後記
日常の中でコーヒーやお茶にほっと癒される時間も、そんな苦味の積み重ねが もたらしてくれていたのかもしれません。
あなたにとって「苦味」は、どんな存在ですか?
今後も食と美意識を考える発信をお届けしていきます。次回もどうぞお楽しみに
最新のコラムはInstagramや各種SNSでもお知らせしますので、
ぜひフォローしてお待ちいただけたら嬉しいです。
現在Apoptosisでは料飲関係者の方を対象にノンアルコールアイテム試飲会を定期的に開催しております。詳細はぜひこちらのページからご確認ください。