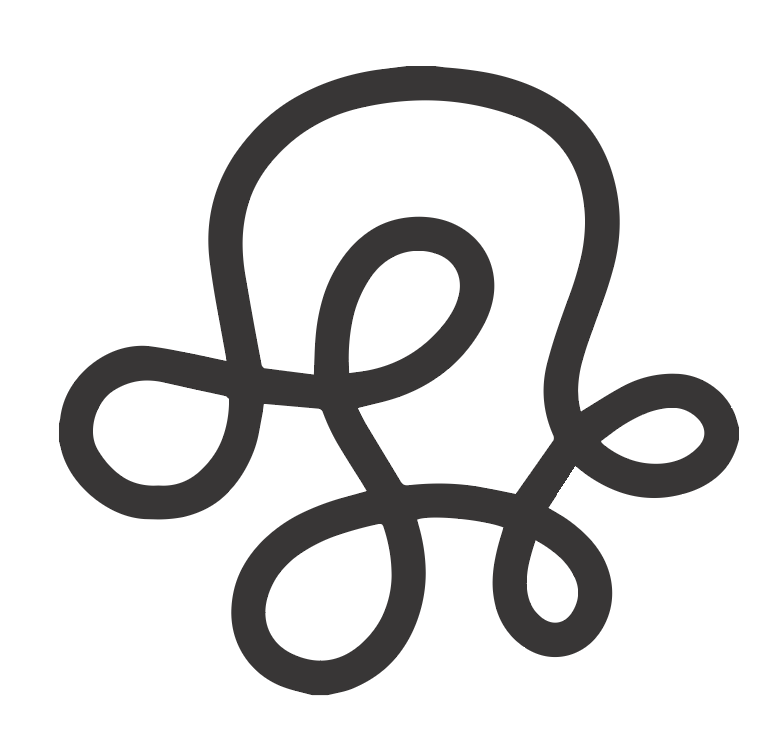テロワールとは何か? 日本茶が映す風土と歴史【#005】
- 2025年7月29日
- 読了時間: 8分
更新日:2025年7月31日
テロワールとは“あるようで、ない”ものかもしれない
___「ワインには、その土地の香りがする」──そんな話を耳にしたことがあります。
“テロワール”と呼ばれるような土地の個性や背景が風味に現れるという考え方でしょうか。
“テロワール”はフランス語で、元々は「土地」を意味する”terre”から派生し、
気候
地形
土壌
農法
などが生産物の風味に影響を与える、という考え方です。
土地特有の個性や香り、味わい──
そういったものは確かに存在するし、生産者の作り方次第で表現される幅も大きく変わります。
ワインやチーズでは「テロワール」という言葉をよく耳にするかもしれません。
ただ、僕自身は、テロワールという言葉をお客様に対して直接使うことはあまりありません。
それは簡単には語り尽くせない奥深い概念だと感じているためです。
僕はむしろ、テロワールとは“あるようで、ないもの”___明言し切れないけれど、探求を促す入口のような存在だと感じています。

“見えない要素”も味わいを構成する
テロワールという考え方は、実は「絵画」にたとえると分かりやすいかもしれません。
たとえば風景画は、目の前の自然を描いたもののように見えます。
でも、その絵が描かれた時の筆の滑りや椅子の座り心地、絵具の質、描き手の感情──すべてが作品に影響しているんです。
___もしその時の椅子の座り心地が悪かったら、画家の気分が乗らず、作品が全く別の仕上がりになったかもしれませんね。
そう考えると、作者やキャンバス、絵の具のような直接的な要素だけでなく、作品を取り巻くすべてが絡み合って、個性につながるように思えます。
まさにその通りです。自然環境だけではなく、
人の営み、道具、気分、時代背景──目に見えないものすべてが味わいに作用している。
テロワールという言葉の裏には、そうした“層”が幾重にも重なっています。

自然と歴史の重なり──土地と人の記憶
その土地でその作物が根付いたのはなぜなのか。
どんな歴史を歩んできたのか。
農作物の味は、風土だけでなく、人びとの味覚や文化ともつながっています。
テロワールとは自然と人間の記憶が混ざり合う「風土のアーカイブ」、記憶装置なのです。
___テロワールの概念はやはりワインにおいて語られることが多いのでしょうか
実は日本茶にもテロワールはあるんですよ。
今回は、わたしたちApoptosisのティープロダクトも含めて日本茶の例をいくつかご紹介します。
日本茶①:浜茶──茶葉が“空気”を吸う
「浜茶(はまちゃ)」と呼ばれるお茶があります。
茶葉を摘んだあと、海辺で天日干しして自然乾燥させたお茶です。
このお茶は、ふわりと磯の風味が立ち上がる独特の個性があります。
例えるならば、まったりとした旨味の中に、
まるでアサリ出汁を思わせるような複雑で奥行きのある味わいになります。
___お茶がフィルターとなってわたしたち海辺の気配を運んでくれるようですね
こうしたお茶を抽出するとき、私たちは個性である“塩気”をどう活かすかを考えます。
茶葉が吸った空気を、どうすれば最も自然に届けられるのか。
その一杯には、浜辺の景色までもが溶け込んでいるのです。
日本茶②:茶草場農法──風景が味に変わる
続いて紹介したいのが、静岡に残る「茶草場(ちゃぐさば)農法」。
これは、茶畑の周囲に生えるススキや野草を刈り取り、畝(うね)に敷き込む「茶草場農法」と呼ばれる伝統手法。世界農業遺産にも認定されている歴史ある農法の名前。
この手法は、野草の香りをじわりと茶葉に移すだけでなく
雑草の抑制
土壌の保湿と保温
有機物の補給
といった効果で土の質も守ってくれる特徴もあります。
この農法で育ったお茶を口にすると、
どこか“笹”のような、ススキのような、
野生みのある香りがふわっと鼻に抜けます。
茶葉がその土地の風景をまるごと記憶しているように感じます。
抽出の際は、この“山の香り”をどう残すかが鍵になります。
お湯の温度を少し下げてじっくり時間をかけることで、やわらかく輪郭のある香りが、そっと引き出されるのです。

日本茶③:和束の太陽と霧が育てる香り
そして最後に京都・和束(わづか)町のお茶をご紹介します。
ここは抹茶の名産地です。
和束は、特徴的に切り立った山の傾斜地に茶畑が広がり、下には細い川。
その斜面と川が非常に特徴的な土地なんですね。

この傾斜の斜面は非常に日当たりが良いです。
勾配があることで茶葉は太陽をしっかり浴びます。
また、足元に通る細い川によって朝になると霧が立ち込めて温度上昇がゆるやかになるため、旨味と香りをじっくり蓄えることができる。
そんな地形と気候が折り重なった風味です。
太陽の光をたっぷり浴びた和束の茶葉は、ほんのり黄みがかった色になります。
僕はそれを「太陽の色だ」と思っています。
花のような香りとナッツのようなコクを育てます。

このお茶を抽出する際は、繊細な香りを壊さないように、
できるだけ静かに、丁寧に。
「この香りを一番美しく届けるには、どの温度がいいか?」
そんなふうに、自然と向き合いながら、表現の選択肢を吟味する時間が生まれます。
こうして生まれた香りを、どんな抽出で届けるか──そこから先は、美意識と試行錯誤の世界です。

“らしさ”をどう届けるか 美意識としてのテロワール
___ここまでお話を聞いていて、お茶の持つ個性の重要性はもちろんですが、
どう抽出するかへの繊細なこだわりも大切だと感じました。
お茶は、どんな風景で育ったかだけでなく、どんなふうに抽出するかによっても、まったく違う表情を見せてくれます。
感じ取った香りや味わいをどう届けるか。
その方法に“正解”はありません。
感性と経験を頼りに、素材の声をすくい取っていくような、静かな試行錯誤の積み重ねです。
私たち提供者は、「どんな表現がふさわしいのか」を突き詰め、お客様に一杯のお茶を届けるわけです。
___素材と向き合いながら、どう届けるかを設計していくのですね
最終的に立ち上がってくる味わいには、生産者の「この風味を届けたい」という美意識が色濃く反映されます。
僕たちのような美味しさを提供する立場は、その素材が生まれた背景を理解したうえで、どうすればその魅力を最も伝えられるか──
その方法を常に探っています。
たとえば、ボトリングティでは、茶葉ごとの個性を活かすために、抽出の温度や時間を細かく調整したり、スパークリングかスティル(無炭酸)かを選んだりします。
その一つひとつの選択が、お茶の“らしさ”を表現するための手段になっているんです。

僕たちはボトリングティのプロダクト開発段階で
やっぱりテロワールとは何か・魅力とは何か僕たちが追い求める美意識は何か____みたいなものは表現に詰め込んでいるつもりです 。
お客様にそれが伝わればいいなと思っています
テロワールとは、感じ、知り、また探求していくもの
テロワールは、1+1=2のような「正解」があるものではありません。
例えるならば作り手と飲み手の両方を「もっと感じとりたい、知りたい」と突き動かす力。
自然環境や農法はたしかに存在しますが、
それがそのまま味になるわけではなく、歴史や文化、人の営みや美意識といった目に見えない要素も含めて感じ取る必要があります。
たとえば、「このお茶、美味しいな」と感じたあとに、
「どういう土地で育ったのか」を知ることで、次に飲んだときの感じ方が変わるかもしれません。
「柑橘の香りがする」と知ってから改めて味わえば、そのニュアンスを感じ取れるようになることもある。
実際、日本茶にもそうした香りの成分が含まれていることがありますよ。
知識が感覚を導き、感覚が知識欲を生む──
そんな循環のなかに、テロワールの面白さがあります。
飲食の提供者は美意識を研ぎ澄まして、そこに込めたい表現を製品に託し「素材の持つ背景や魅力をどう伝えるか」を日々考えています。
その積み重ねのなかに、たしかに“テロワール的なもの”は息づいています。
きっとそれは「正解を探す」のではなく「感じて、考えて、また感じていく」
──そんな終わりのない冒険なのかもしれません。
冒険だからこそ、わかる・わからないという成果だけではなく、その道程を素直に楽しむ事も出来る。
そんな人生の余白のようなものを、お茶やお酒を通して感じられるのはテロワールという概念の魅力のひとつですね。
編集後記
今回は、テロワールをテーマにローレンスさんにお話を伺いました。
専門的で難しい世界かと思っていましたが、
まずは自由に味わい、感じ取ったことと 少しの知識を行き来しながら、じっくり発見を深めていけばいいのかもしれないと気づけました。
これからも、美意識の旅へ誘う記事をお届けします。
次回もどうぞお楽しみに。
最新のコラムはInstagramや各種SNSでもお知らせしますので、
ぜひフォローしてお待ちいただけたら嬉しいです。
現在Apoptosisでは料飲関係者の方を対象にノンアルコールアイテム試飲会を定期的に開催しております。詳細はぜひこちらのページからご確認ください。