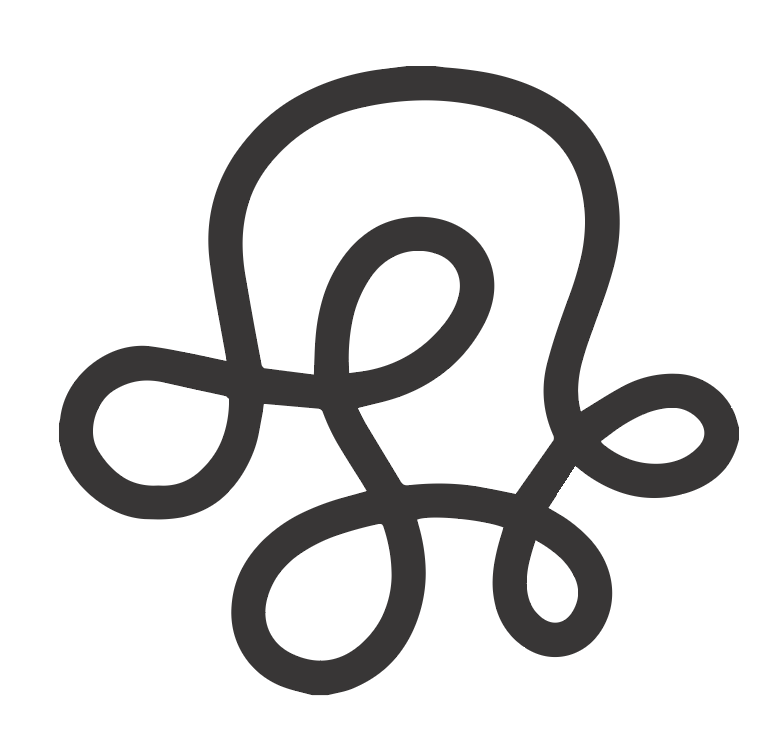一滴の水に宿る土地の記憶 水と食文化【#004】
- 2025年7月21日
- 読了時間: 9分
更新日:2025年7月31日
水は通った道で味が変わる
飲んでいる水はH₂O「だけ」ではない
___水そのものは味に違いがあるんでしょうか?
まず、普段私たちが触れる水は H₂Oだけではない ということはご存知ですか。
学校の理科で学ぶ“純水”は、水素2つと酸素1つでできたシンプルな構造ですよね。
でも、僕たちが日常的に飲んでいる水には、実は さまざまな成分が微量に含まれている んです。
自然界の水は、土や岩を通る中でいろんなミネラルや物質を少しずつ溶かし込んでくる。
だから、一見同じように見える水でも、通ってきたルートによって味や舌ざわりがまったく違うんです。
___ということは、水は“どこを通ってきたか”で味が変わるんですね。
そうですね。
山の水、地下水、川の水、そしてそれぞれの地域の水道水___。
すべてが、通ってきた道のりと、接触してきた地層や成分によって、個性を持っています。
だから、水の味を辿るってことは、土地の記憶をたどることでもあるんです。

軟水と硬水のちがい
鉱物との接触時間と“硬度”
___「硬水」と「軟水」と聞きますが、具体的にどう違うんですか?
簡単に言うと、水の中にどれだけ“ミネラル”が溶け込んでいるかなんです。
特にカルシウムやマグネシウムといった成分の含有量の違いが、「硬水」「軟水」という区分を生み出します。
___なるほど。ヨーロッパの水は“硬水”、日本の水は“軟水”が多いと聞いたことがあります。
そうですね。
これは地形の違いがすごく大きくて。
ヨーロッパは大陸なので、山も川もとにかくスケールが大きい。
たとえばアルプス山脈のような広大な山々を源にして、長い時間をかけて地中を通ってくる水が多いんです。
途中でいろんな地層や鉱物に触れるので、ミネラルがたっぷり溶け込んで、硬水になります。

一方、日本は島国で、国土全体が“でこぼこ”しているんですよね。
山が多くて、川は短くて急流が多い。
雨が山に降ってから海に流れ出るまでの距離がすごく短いんです。
急流で接触時間が短いぶん、地層から取り込む成分も少ない。
その結果、日本では自然と軟水が多くなるんです。
___水の硬度には、地形や地質が深く関係してるのですね。
※)「接触時間」だけでなく「地質」も水の硬度に影響
日本は火山由来の地質でミネラルが溶け出しにくいため軟水が主流。
一方、ヨーロッパは石灰岩などの地層が多く、ミネラルが溶け出しやすく硬水になりやすいのが特徴。

舌で感じる、水の“やわらかさ”と“シャープさ”
___水の“硬い、やわらかい”って実際に感じられるものなんですか?
はい。たとえば軟水は、舌の上で「じんわり広がる」ような滑らかさがあります。
スッと消えていくような、平面的でやわらかい印象ですね。
逆に硬水は、どこかで“スパッと切れる”ような舌ざわりがあるというか、
味がはっきりしていて、シャープに感じる方もいると思います。
___言われてみれば、海外のミネラルウォーターってちょっと舌触りがちがうと感じることがありますね。
そうですね。
日本の水に慣れていると、硬水には“くっきりした存在感”を感じることもあります。

水と文化
出汁文化が育つ“軟水の国”日本
___水の違いは、地域の特性にも影響しているのでしょうか?
水とその土地の文化や料理は関係が深い。
たとえば日本には、鰹や昆布から丁寧に出汁を取る文化がありますが、これは“ミネラルの少ない軟水”だからこそ。
硬水で出汁を取ろうとすると、成分がうまく抽出されなかったり、香りが立ちにくくなってしまうんですよ。
※)硬水はカルシウムやマグネシウムといったミネラルが、
昆布のアルギン酸やグルタミン酸と結びつき成分の抽出を妨げてしまうため出汁がとりにくい。
昆布の表面がかたくなったり、うま味や香りも出にくくなる。
一方で軟水はこうした反応が起こりにくく、素材の持ち味を素直に引き出してくれる。
___なるほど、水の性質が料理の基本にまで関わってくるんですね。
そうなんです。日本の中でもさらに地域によって違いがあるんですよ。
たとえば本州は比較的やわらかい軟水で、まさに出汁文化が育ちやすい環境です。
一方で、沖縄の水は“軟水”には分類されますが、琉球石灰岩という地層を通ってくるため、 硬度は本州よりやや高め。
沖縄の水はミネラル感がしっかりしていて、豚の出汁や油を活かした料理と相性が良いんです。
動物性の旨みや油をすっきりまとめてくれる水ですね。
ソーキそばのような豚骨ベースの料理は沖縄の水に合ったスタイルともいえますね。
水と調理環境
水は料理方法や火力にも関係します。
日本の「コトコト煮る」調理法は、クセのない軟水ととても相性がいい。
逆に中華料理のように、“強火で一気に仕上げる”スタイルは、水に個性があるからこそ活きてくるんです。中国は川の流れがゆるやかで、水に少し“土壌由来の風味”が残ることがあります。
そういった水を使う場合は、いきなり茹でるのではなく、まず油で素揚げしてから煮るという調理法がよく使われます。
この話は“調理器具、キッチンのつくり”にまでつながっていきます。
中国では古来から石炭など強い火力で料理していた事が知られています。
特に中国の宋代になると、「鉄鍋」の精製が可能になります。
その鉄鍋は火力を逃さないように底が丸い形状をしているんですね。
___いわゆる「中華鍋」と言われてイメージする鍋は、底が丸くて強火の調理に使用される様子が浮かびますね
そしてかまども、大きな火口がひとつドンと構えてあって、大鍋を振れる構造になってきます。そうすると現代の私たちも大好きな中華料理のカテゴリー、炒め物も発展していきます。
高火力に耐えられる台所用品と構造により、加熱時間も長く取れるので、蒸し料理も発展し、スープも食材から徹底的に味わいを煮出す事が出来ます。
加えて香辛料などの複雑な風味も重なり、長江、黄河に代表される大河流域において、多彩で華やかな食文化を形成してきました。

それに対して日本の台所は、ご飯を炊くかまど、煮焼きをする大小の囲炉裏と細かく分かれています。
火加減を丁寧に調整することを前提に設計されているんですね。
火力も基本的には薪や炭です。
和食の代表的な要(昆布出汁や鰹出汁)も、
低温またはサッと加熱して一番良い部分だけを抽出します。
長時間煮出す事はあまりありません。
これは水が新鮮なのでシンプルに茹でたり煮るだけで美味しいし、味わいは醤油、タレ、汁で外からつけられるといった理由からです。
そう考えると、水って味を左右するだけじゃなくて、文化を形作るのに大きな存在なんです。

地形がつくる水の個性
県内でも“水のバリエーション”を生む 山形の事例
僕の故郷、山形県の話をします。
山形県内にあるふたつの酒蔵は,使っている水の硬度がまったく違うんです。
同じ県内にあり、“30kmも離れていないのに”、水が通ってきた道のりや地層の違いで、性質も味わいもがらりと変わってくるんです。
___県内同士で近い距離でも、水が違うんですね。
ひとつは裏山を水源にした軟水。
軟水の蔵では、硬度30以下の非常にやわらかい水。
もうひとつは、北側の大山脈から長い時間をかけて流れてくる硬水。
硬水の蔵は、硬度140ほど。
およそ5倍の差があります。
この違いが、発酵の進み方や香りの立ち方、そしてお酒の“キレ”にまで影響を及ぼしているんです。
___地質と水質の関係が密接だと理解できてきました。
では、もうひとつ、異なる角度からの事例をお話しします。
今度は山口県の話。
山口県は本州の西の端に位置していて、東西に細長く、南北の幅は比較的コンパクトな地形です。
そのため、川の流域が限られ、水が海へ流れ出るまでの距離も短めなんです。
それなのに、山口県の水には“硬水”が多く存在します。
___これまでのお話で「短い川は軟水/大規模な川は硬水」という傾向だと思っていました。
でも山口県の場合は短い川でも硬水ができるのはなぜでしょうか
一見すると、川の長さも短く、軟水になりそうに思えるかもしれません。
でも山口県の地中がとても入り組んでいて、
水が多くの地層と長い時間をかけて接触するため、しっかりとした硬水になっているんです。
___複雑な地層の影響で硬水になるのですね。
例えば山口にある日本酒「貴(たか)」は、
この複雑な地層を通った山口ならではの硬水で仕込まれています。
ミネラルが豊富な硬水は、酵母の発酵を勢いよくスタートさせます。
お米をしっかり溶かし、旨味はきちんと残す。
そこに硬水特有のシャープな舌ざわりが重なることで、
キレがありながらも厚みのある、引き締まった酒が生まれるのです。
地質が語る日本列島の記憶
___そもそも、なぜ山口県にはこんなに特徴的な地質が見られるのでしょうか?
実はこの話、日本列島の成り立ちにも関わってくるんです。
日本列島って、だいたい1億年前くらいまでは、まだユーラシア大陸とくっついていたんですよ。
それが少しずつ引き離されていって、5000万年前ごろから、いま日本列島のような“弓なり”の形になっていきます。
約3000万~1500万年前、日本海がゆっくりと開いていくなかで、日本列島は大陸から少しずつ引き離されていきました。
山口県を含む西日本は、その“引き離される前”の大陸のふちにあたる場所で、大陸と一体だったころの約1億年前の古い地層が今も地表に多く露出している地域なんです。
___壮大な時間軸の話ですね
さらにその後、火山活動が活発だった時期には、カルデラや火砕流が各地に広がって、
山口県には分厚くて複雑な地層が重なっていきました。
こうした地層の重なりや、岩の組成、地下にできた“すき間”が、水の通り道になっていく。
結果、ミネラル豊富な水が生まれるんです。

水は哲学の入り口になる
見慣れた一杯の水の奥に、新しい世界がある
僕にとって、水ってロマンなんですよね。
たった一口の水の中に、何十万年、何億年っていう土地の記憶が溶け込んでいる。
そこに生きてきた人たちの営みや、自然の造形、文化の工夫までもが、
味わいというかたちで立ち上がってくる。
そんな風に感じると、水を飲むたびに「物語が始まる」ような感覚があるんです。
___一杯の水から、こんなにも深い話になるとは思ってもいませんでした。
水の違いを知ることで、その土地の歴史や文化、
さらには料理法や家のつくりにまでつながっていく。
本当に「味わう」って、壮大な旅の入り口みたいですね。
水って、ふだんあまりにも当たり前にそばにあるものだけど、
そこをちょっと深掘りしてみると、食の見え方も変わってくると思います。
もし「味わい」をもう一歩深めてみたいなって思ったときは、
ぜひ「水」から掘り下げてみてください。
きっと新しい視点が見えてくると思いますよ。
編集後記
今回は、水の味わいへの驚きから始まり、 味、文化、地形、そして時間──思いがけない広がりのあるお話になりました。
これから飲む一杯の水も、ちょっと違って感じられるかもしれません。
また次回も、どうぞお楽しみに。
最新のコラムはInstagramや各種SNSでもお知らせしますので、
ぜひフォローしてお待ちいただけたら嬉しいです。
現在Apoptosisでは料飲関係者の方を対象にノンアルコールアイテム試飲会を定期的に開催しております。詳細はぜひこちらのページからご確認ください。