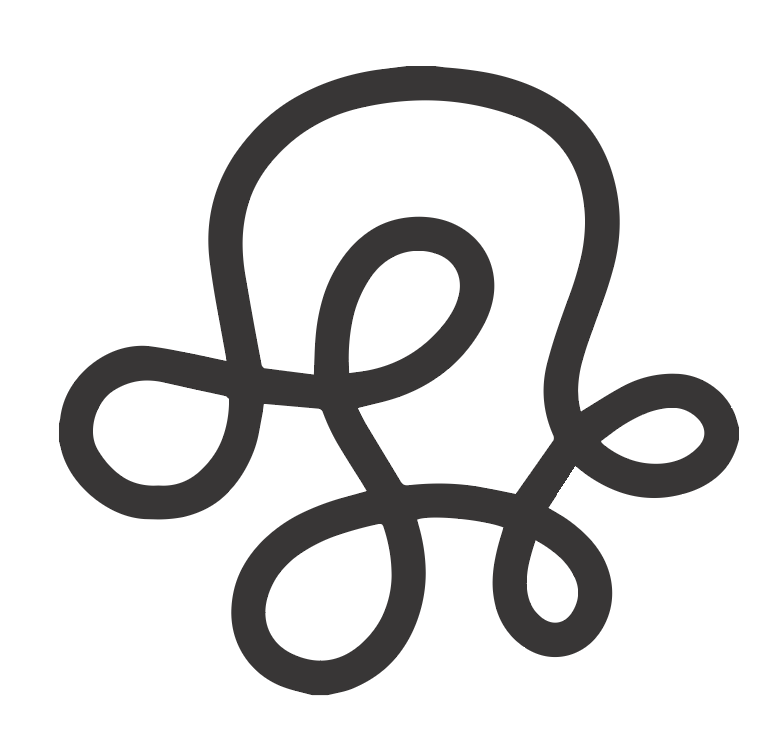香りのもたらす効果 美味しさと癒しの関係【#003】
- 2025年7月15日
- 読了時間: 5分
更新日:2025年7月31日
舌は“強度”を、鼻は“質”を測る
──「 味覚よりも、嗅覚が味に大きく関わっている」という話を聞いたことがあります。
舌より鼻の方が優位なのでしょうか?
ローレンスさんはどう捉えていらっしゃいますか?
味覚と嗅覚はどちらが“劣っている/優れている”と比較するものではなく、
役割が違います。
それぞれ「得意分野」があるんです。
たとえば、香り=嗅覚は“質”を測るのが得意。
素材が何か、特徴は何か、といった質的情報を感じ取る能力ですね。
一方で、舌=味覚は“強度”を測るのが得意。
塩分濃度とか、硬さとか、「強すぎる・弱すぎる」といった量的な情報。
人間の感覚には、それぞれの“専門領域”があるということです。
五感は“安全装置”でもある
動物はまず「匂いを嗅ぐ」ことで、食べられるかどうかを判断してるんです。
人間も、たとえば、賞味期限切れの納豆。「いけるかな?」と思っても、まず“嗅ぎます”よね。
香りは、危険信号をキャッチする“最初のチェックポイント”なんです。
そこから口に入れて、舌で味を感じ、口腔内から鼻へ香りが戻ってくる。
それら全部が合わさって、最終的な「味」が完成する。
五感って、感性のためだけじゃなく“安全装置”としても働いてるんですよね。

フレーバーとは何か──脳がつくる“味の編集”
──- たとえば紅茶や出汁をいただくとき、香りや味をまるごと楽しんでいる気がします。
実際、私たちが「これは美味しい」と感じるときって、何がどう組み合わさっているんでしょう?
すごく大事な視点ですね。
まず、前提として「香り」と「フレーバー」は別物なんです。
香りを嗅いで、口に入れて、味を感じて、さらに口腔内から鼻へ戻ってくる香りまで含めて、
脳が総合的に判断して「これは◯◯味だ」と認識する
─それがフレーバーです。
つまり、味とは単なる味覚ではなく、五感の合成による“脳内の編集結果”なんです。
香りは連想ゲームのように広がる
香りや温度、色、食感──それらの組み合わせによって、まったく別の味に感じてしまうことがある。
つまり、美味しさって“記憶の編集”でもあるんですよ。
香りやフレーバーは連想ゲームのように広がり、時には錯覚することもある。
たとえば、屋台で見かけるかき氷のシロップ。
あれは「メロン味」と書いてあっても、実はメロン果汁が入っていないことも多いんです。
でも、緑の色・冷たさ・甘さ・酸味が組み合わさると、「これはメロン味だ!」と錯覚してしまう。
もう一つの例は、ロングアイランド・アイスティー。
お茶は一滴も入っていないのに、いろんなお酒と香りが重なって、「アイスティーっぽい」と脳が感じてしまう。
これも完全に“錯覚”ですね。

感じることそのものが、癒しになる
── アロマなどいい香りにはリラックス効果があるとよく聞きますよね。
そうですね。でも僕は、「この香りは○○に効く」って効果効能を断定するのは、ちょっと違和感があるんです。
大切なのは、「この香りを感じることで、自分がどう変化するか」という“体験そのもの”を楽しむこと。
「効く」かどうかじゃなくて、「今の自分が何かを感じられているかどうか」が、本質的には大事なんです。
感覚に意識を向ける時間こそが、結果として癒しになる。

IPAビールやジンに見る、「強く感じたい」欲求
____感覚に意識を向ける時間。
これは、忙しい日常において、置いてきぼりになりがちですね。
香りに限らず、「何かを感じる」という行為そのものが、ストレスの緩和につながっています。
嗅覚や五感が鈍ってくると、知らないうちにストレスがたまっていくんですよね。
だから人間は、辛味・酸味・冷たさのような“強い刺激”を求めて、
感覚のリセットをしようとする。
たとえば、最近人気のIPAビールやジン。
※IPA(インディア・ペール・エール)は、ホップを多く使ったビール。
柑橘系や花のような豊かな香りと、しっかりした苦味が特徴。
クラフトビールの代表的なスタイルとして人気が高まっている。
これらに共通するのは、香りのインパクトが強いことです。
これって、ストレス社会の裏返しかもしれない。
「何かを強く感じたい」という無意識の欲求が、刺激のあるものに向かわせているんです。

「感じられるかどうか」が、今の自分を映す
── なるほど
どんなものに惹かれるかに、実は「いまの自分の状態」のサインが出てるのかもしれませんね。
香りや味を“正しく理解する”ことよりも、「ちゃんと感じられているかどうか」のほうが、むしろ自分の状態を知る手がかりになります。
分からなくても、感じなくても、いいんです。
ときには「分からないまま楽しむ」余裕がいちばん大切。
もしその余裕がなくなっていたら……
何か無理に行動するより、まずは寝たほうがいい(笑)。
情報を詰め込みすぎず、香りと自分をやさしくつなぐ時間を、大事にしていきましょう。

今回は、香りをテーマにお届けしました。
香りを感じるという行為は、
実は「いまの自分の状態をそっと捉えること」に近いのかもしれません。
忙しさに追われる日々の中でも、ふと香りに意識を向けるだけで、
ほんの少し、自分自身を取り戻せる瞬間が生まれるはずです。
今後も美味しさとは?をさまざまな角度から探求していきます。
次回もどうぞお楽しみに。
📣 コラムの更新情報はInstagramでもお知らせしています。ぜひフォローをよろしくおねがいします!
現在Apoptosisでは料飲関係者の方を対象にノンアルコールアイテム試飲会を定期的に開催しております。詳細はぜひこちらのページからご確認ください。