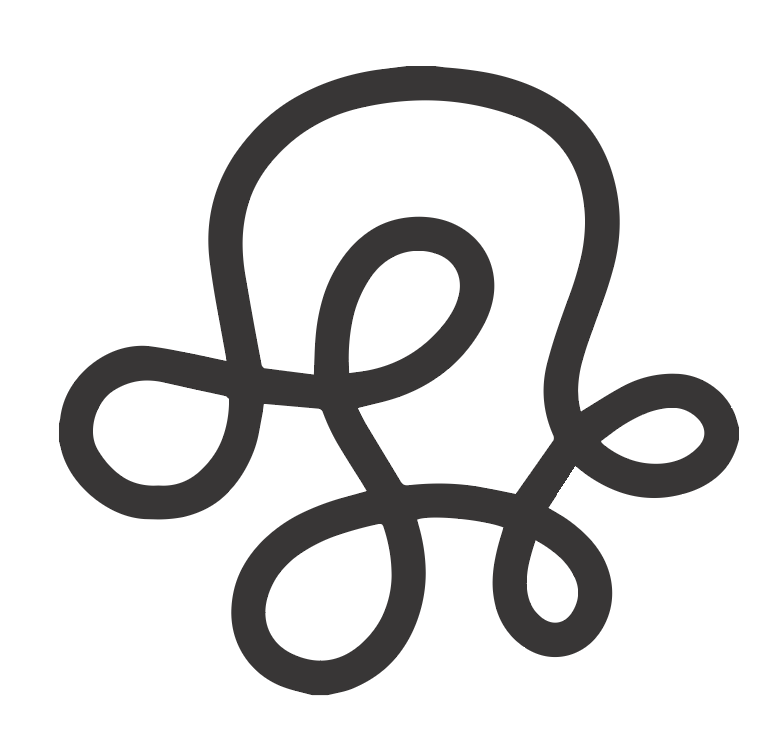「香りと美味しさ」からパーソナライズと五感設計を考える【#002】
- 2025年7月14日
- 読了時間: 5分
更新日:2025年7月31日
味覚を通して、人間を探る
── ローレンスさんに質問です。
人はどんなときに「美味しい」と感じるのでしょうか?
美味しいを一言で説明するのはとても難しいですよね。
正直な話を言うと、このテーマで最初に出すべき“答え”は、「答えは、ない」なんですよ(笑)。
でも、だからこそ面白い。
人によって感じ方が違う、状況によっても違う
──その“ゆらぎ”の中にこそ、美味しさの魅力があると思うんです。
美味しさとは、単なる感覚の話ではなく、「人間とは何か?」を考える入り口にもなります。
ちょっとカッコつけて言うなら、これは“冒険”です。
味覚、香り、記憶……それらをたどっていくと、どこかで「自分自身」に出会える気がする。
「味覚ってなんだろう」をきっかけに「人間ってなんだろう」を考える……
己の探求の時間かもしれないですね。
美味しさは“設計する”もの
多くの人は、美味しさを「受け取る」側で体験しています。
しかし、美味しさの作り手側から見ると、その景色は大きく変わります。
僕らのように「発信する側」──つまり、どうやって美味しさを感じてもらうかを設計する側から見ると、見え方が変わるんです。
たとえば「どんな順番で味を伝えるか」とか、「どんな空間で飲んでもらうか」とか。
それ次第で、まったく同じ飲み物だとしても印象が変わります。
感覚が遮られると、美味しさは消える?

あえて「五感が鈍る場面」の話をしてみましょう。
テレビ番組の“目隠しをしてワイン当て企画”を思い浮かべてみてください。
アイマスクで視覚が遮断され、さらにはスタジオ収録の緊張感。
スプーン1杯の少量のワインで香りも立ちにくい状況ですね。
香りが抑えられると判別がさらに困難になります。
香りって記憶と直結してる感覚なので、緊張状態だと記憶が引き出しにくくなってしまうんですよね。
しかも、スタジオ収録という緊張環境下では、芸能人の方々も「間違えられない」とか「ウケなきゃ」といったプレッシャーを感じていて、五感が鈍る。
この環境ではプロでもワインを当てるのは至難の業です。
── たしかに、五感が鈍ると全く味わいが変わってしまうのが想像できます。
だからあのような番組企画は「人がどのように味を感じているか」を示す、いい実験にもなってるんです。
── ということは、逆に「五感を感じやすい状況」をつくることで、美味しさを最大化できるということですか?
ローレンス:
まさに。そのためには、五感を活かせる“場”をどう設計するかが鍵です。
味わいは、空間と空気でも決まる

たとえば、清潔なオープンキッチン。
視覚的に「丁寧に料理してる」「衛生的だ」と感じられれば、それだけで“味”の受け取り方が変わります。
逆に、同じ料理でも、キッチンが汚れていたら、「え、大丈夫かな……?」と不安になってしまう。
それだけで、舌にのせる前に印象が変わってしまうんです。
いま目の前で調理されてる「ライブ感」や、「真心のおもてなし」などもワクワクして、食べる前から美味しさの期待値が上がります。
結局、美味しさって「味」だけじゃなくて、空間や空気、振る舞いまで含めた総合的な体験なんですよね。

美味しさは“パーソナライズされた記憶”で届く
__「美味しさの届け方」を設計するときに他にも意識することを教えてください。
伝える相手に合わせること、つまり「パーソナライズ」が大事なんです。
例えば、僕がソムリエとしてワインの説明をするとき、日本人には「ドクダミの香り」って表現を使うことがあるんです。
ナチュラルワインの、ちょっと癖のあるタイプにはすごく合う。
でも、これって海外では通じないんですよね。ドクダミそのものを知らないからです。
だから、相手の文化圏にあわせて、表現の言葉を変える必要がある。
── 言葉のニュアンスや、何を知っているかの前提は文化によって大きく違いますもんね。
そう。だから相手がどういう文化圏で、どういう味や香りに親しんでいるのか
──それを知ることが、美味しさを届ける第一歩になる。
食を伝えるうえでは、「一般化された理解」も必要です。
でも同時に、「その人にとって刺さる味や言葉は何か?」を考え続けることも大事。
文化・食習慣・宗教・体験──そういった背景に合わせて、香りや味を届けていく。
結局、美味しさって“パーソナライズされた記憶の引き出し”を、どれだけ丁寧に開けていけるかだと思うんです。
情報の量も、“おいしさ設計”の一部
パーソナライズには、情報の量も関係します。
たとえばワインの香りをソムリエが複雑に言いすぎてしまうと、
「自分はそんなに繊細に感じられない」と、お客さんを萎縮させてしまうこともある。
情報をたくさん伝えることが、必ずしも毎回良い結果を生むわけじゃない。
“どれだけ伝えるか”を選ぶことも、時にあえてそぎ落としてシンプルに伝えることも設計のひとつなんです。
たくさんの情報よりも、その人がその一杯を「美味しい」と思ってくれることが大切。
感じてもらうために、時には説明しすぎない“余白”が必要な場面もあるんですよね。
今回は「美味しさを届けるとは?」という視点で、ローレンスさんにお話を伺いました。
──誰に、どんな体験をしてもらいたいのか。
そのために、どう設計するのか。
その人にあったパーソナライズとは。
この問いと向き合うことは、美味しさの届け方をあらためて見つめ直すきっかけになるかもしれません。
次回は、「香りは味を決めるのか?」という問いを手がかりに、
味覚と嗅覚の関係をひもといていきます。
どうぞお楽しみに。
最新のコラムはInstagramや各種SNSでもお知らせしますので、
ぜひフォローしてお待ちいただけたら嬉しいです。
現在Apoptosisでは料飲関係者の方を対象にノンアルコールアイテム試飲会を定期的に開催しております。詳細はぜひこちらのページからご確認ください。