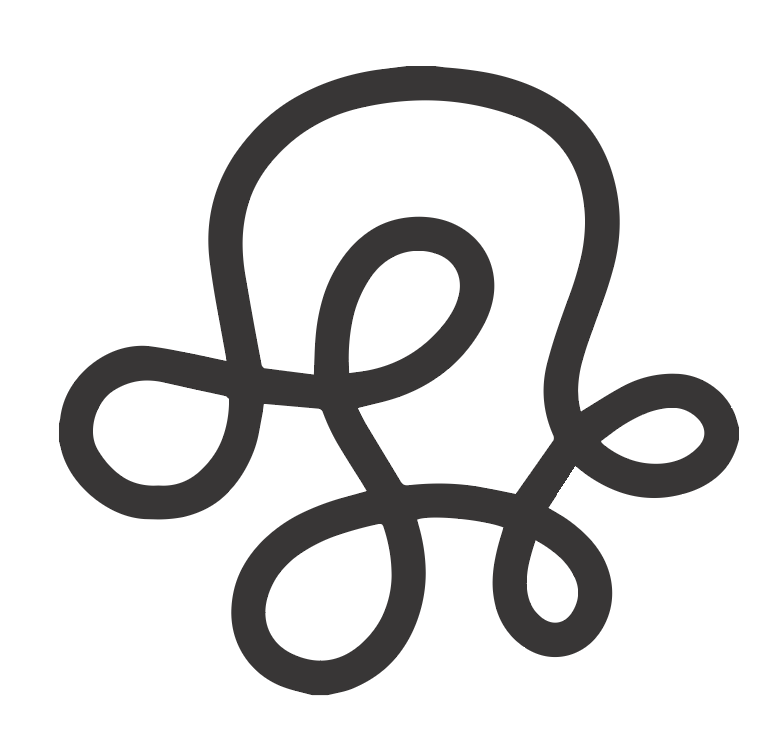美味しさは “要素の複合” でできている【#001】
- 2025年7月14日
- 読了時間: 4分
更新日:2025年7月31日

美味しさは感覚を総動員
_____美味しいって、そもそも一体何なのでしょうか
とてもシンプルだけど、奥が深いテーマですね。
例えば、乾杯して「美味しいね」って言うとき、実は僕たちは香りをかいだり、温度を感じたり、 いろんな感覚を総動員してるんですよね。
“美味しい”って、単なる味じゃなくて、複雑な感覚のかたまりなんです。
美味しさにはいろんな要素がある。
少し専門的な話になりますが、美味しさは様々な要素に分けて捉えることができます。
例えば生理学、文化、情報、快楽 など...
少し掘り下げてみますね。

生理学的な美味しさ
たとえば、 暑い日に冷たい飲み物で体を冷やしたくなるとか、
疲れたときに甘い物が欲しくなる。
これは身体が発している「必要」のサインであり、もっとも原始的な“美味しさ”です。

文化的な美味しさ
地域文化や歴史の影響が味覚に与える影響って、大きいんですよ。
習慣によって「美味しさの基準」も変わってくるんです。
例えば、僕の地元山形には「納豆汁」という郷土料理があります。
こちらは納豆をすりつぶして味噌と合わせた、冬の定番ともいえる温かい汁物です。
さらにラーメン文化がとても盛んで、その中でも少し変わり種として知られているのが「納豆ラーメン」。
納豆をトッピングしたラーメンで、地元ではなじみ深い存在です。
もともと納豆をあまり食べない、または料理に取り入れる文化がなければ、「えっ!?」と驚かれるのも無理はないですし、素直に美味しいと感じられない可能性もありますよね。

情報による美味しさ
「これは超高級な〇〇です」「これは貴重な食材です」と言われると、やっぱり美味しく感じたりしますよね。
あるいは、お店の雰囲気や器、照明── そうした“情報や演出”も、味覚に影響してきます。 これはちょっとした“思い込み”でもあるけど、それもまた美味しさの一部です。

空間の情報も大きく影響します。
たとえば、清潔なオープンキッチンを想像してみてください。
視覚的に「丁寧に料理している」「衛生的だ」と感じられれば、それだけで料理への安心感や信頼感が増し、実際の“味わい”もよりポジティブに感じられるようになります。
さらに、香りや音、手さばきなどを目で追えるライブ感は、「美味しそう!」というワクワク感や高揚感を引き出してくれるものです。
逆に、同じ料理でもキッチンが雑然としていたり、空間が暗く閉鎖的だったりすると、無意識のうちに「え、大丈夫かな……?」という不安がよぎる。
その印象だけで、実際の味まで変わって感じられることもあります。
つまり、空間は、まだ味わっていない“前の段階”で、すでに美味しさを左右している要素なんです。
快楽としての美味しさ
これはもう、考えるより先に体が覚えているような“中毒性”ですね。
僕、子どもの頃にコーラが大好きで。 いまソムリエとして働いていても、たまに「コーラ飲みたい!」って思うんです。
何万円のワインを飲んだあとでも(笑)。
これはもう、思考じゃなくて欲求。 中毒的に体が覚えてる快楽です。

美味しさを“届ける”という視点
_____なるほど…!いろんな感覚や背景が重なってるんですね。
そうなんです。
僕たちは、お茶やワインといった「味わいを設計する側の立場」なので、 これらの要素をどう組み合わせるかを常に考えています。
たとえば、
・この茶葉のどこが魅力的なのか?
・どんなふうに届けたらその良さが伝わるのか?
味そのものももちろん大事なんですが、それ以上に「どう届けるか」 「どう感じてもらうか」の視点が大切。
そこまでを設計するのが、僕たちの仕事なんです。
だから、“どんな価値をどう伝えるか”の糸口を見つけることが、美味しさをつくる仕事の本質だと思っています。
美味しさは単なる“味”ではなく、 身体、文化、情報、そして記憶や快楽 までを巻き込んだ総合的な感覚。
そして、それをどう届けるかまで考えたとき、 飲食の世界は、もっと豊かに、面白くなっていきますね。

今回は「美味しさとは?」の入り口をほんの少し垣間見ることができました。とても奥深い世界。
次回は「香り」をテーマに、美味しさの裏側にある“記憶”や“感情”についてローレンスさんに伺っていきます。 どうぞお楽しみに
最新のコラムはInstagramや各種SNSでもお知らせしますので、
ぜひフォローしてお待ちいただけたら嬉しいです。
現在Apoptosisでは料飲関係者の方を対象にノンアルコールアイテム試飲会を定期的に開催しております。詳細はぜひこちらのページからご確認ください。